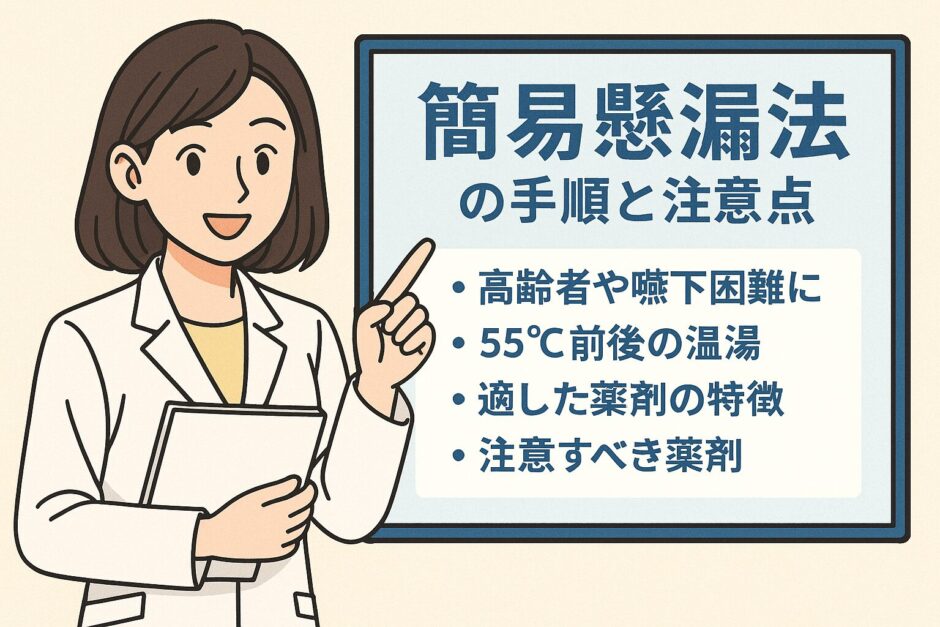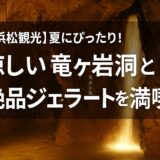在宅医療や高齢者施設での服薬支援に携わる薬剤師の皆さん、こんなお悩みはありませんか?
「錠剤をそのまま飲めない患者さんが多いけど、粉砕だと手間や誤飲のリスクがある…」
「簡易懸濁法を導入したいけど、どの薬がダメなのか自信がない…」
実は、簡易懸濁法は正しく活用すれば、患者さんにも薬剤師にも大きなメリットがある手技です。
なぜなら、服薬コンプライアンスを改善しながら、薬効や安全性を保つことができるからです。
私自身、病院薬剤師時代に何度も簡易懸濁法の指導や運用を担当し、多くの現場で「知らなかった」ことによる事故を防いできました。
「この薬、簡易懸濁ダメだったんだ…」という声は、意外にも少なくありません。
この記事を読むと、次のようなことがわかります。
- 簡易懸濁法の基本的な流れと実施手順
- どんな薬剤が簡易懸濁に向いているのか
- 注意すべき薬剤の具体例と理由
- 現場でのトラブルを防ぐための工夫
- 添付文書や医師への確認ポイント
つまり、薬剤師として簡易懸濁法を自信をもって活用し、安全な服薬支援ができるようになります。
もくじ
簡易懸濁法とは?服薬支援に欠かせない調剤手法
簡易懸濁法とは、錠剤やカプセル剤をそのまま水または温湯に浸して軟らかくし、崩壊・懸濁させて服用しやすくする方法です。
高齢者や嚥下困難患者に最適な方法
この方法は、粉砕や分包が不要なため、作業の簡略化と誤薬リスクの低減に貢献します。
薬効保持のメリットも
粉砕不可の薬剤でも、簡易懸濁なら使用可能なケースもあり、有効性の維持にも役立ちます。
簡易懸濁法の基本的な手順とポイント
手順を守ることで、薬効の保持と安全な投与が実現します。
図解でわかる簡易懸濁法の基本ステップ:

手順の概要
- 錠剤やカプセルをコップに入れる
- 55℃前後の温湯(100mL)を注ぐ
- 10〜15分程度放置し、崩壊・懸濁を待つ
- よくかき混ぜて服用または経管投与
ポイント
- 温度は重要:高すぎると薬剤が分解する恐れがあります
- 放置時間は薬剤により調整が必要です
- 使用後は速やかに投与する(安定性の問題)
簡易懸濁法が向いている薬剤とその理由
簡易懸濁法に適した薬剤には共通点があります。
適した薬剤の特徴
- 水または温湯で速やかに崩壊する
- 徐放性でない
- 腸溶性コーティングでない
- 安定性が高い(pHや温度に強い)
一例
- カロナール錠
- アムロジン錠
- アリセプト錠
- ニフェジピン普通錠(徐放性でないもの)
簡易懸濁法で注意が必要な薬剤の具体例
以下の薬剤は簡易懸濁法で特に注意が必要です。
| 分類 | 具体的な薬剤 | 注意点 |
|---|---|---|
| 徐放性製剤・腸溶性製剤 | アダラートCR錠、アダラートL錠、デパケンR錠、セレニカR錠、 テオドール錠、スローケー錠、タケプロンOD錠、アデホスコーワ顆粒 | 特殊構造が壊れると薬効が変化し、副作用リスクが増加するため使用不可 |
| 温湯で安定性が保てない薬剤 | シクロフォスファミド、カリジノゲナーゼ(55℃で分解) | 温湯によって分解・効果減弱の恐れがある |
| 配合変化を起こしやすい組み合わせ | レボドパ製剤+鉄剤、レボドパ製剤+酸化マグネシウム製剤、 塩化ナトリウム+他薬剤(単独懸濁推奨) | 化学反応や沈殿、効果減弱が発生するため組み合わせに注意 |
| 水や温湯で溶けにくい・分散しない薬剤 | コロネル錠、セレキノン錠、ダイドロネル錠、オフタルムK錠、ガストローム顆粒 | 十分に崩壊・懸濁せず、投与困難またはチューブ閉塞の恐れあり |
| その他注意薬剤 | テオドールドライシロップ(懸濁後すぐ注入)、エブランチルカプセル、クラビット | 薬剤によっては速やかな投与や配合変化の確認が必要 |
これらの薬剤は、添付文書や医師の指示を必ず確認しましょう。
どうしてNGなのか?懸濁に適さない薬剤の特徴
薬剤の構造や性質によって、簡易懸濁が不適切になる理由を理解しましょう。
徐放性・腸溶性は構造が命
コーティングが剥がれると、急激な血中濃度上昇や副作用リスクが高まります。
熱に弱い薬剤は分解の危険
シクロフォスファミドのように温湯で不安定な薬剤は、効力が落ちるだけでなく有害成分が出ることも。
配合変化の問題
薬剤同士のpHや化学的性質で沈殿や変色、効果の消失が起きるケースがあります。
簡易懸濁法を導入する上での現場対応と工夫
施設や病棟での運用に際しては、以下の工夫が役立ちます。
懸濁できる薬剤一覧を作成
現場スタッフや介護職とも共有できるリストを準備しておくと安心です。
投与時間に余裕を持たせる
懸濁に時間がかかる薬剤は、あらかじめタイマー管理で準備を。
チームでの情報共有を
医師・看護師との連携を密にし、適宜薬剤変更を提案できる体制づくりを。
簡易懸濁法を正しく理解し安全な服薬支援を実現しよう
- 簡易懸濁法は服薬支援の現場で有効な調剤手法
- 向いている薬剤・向かない薬剤を正確に把握することが大切
- 徐放性・腸溶性・熱に弱い薬剤は特に注意が必要
- 配合変化や安定性の観点からも個別に判断
- 現場ではリスト化や情報共有が安全性を高める鍵
適切な知識と判断で、安全・確実な服薬支援を実践しましょう。